赤ちゃんが生まれたら、将来必要になる学費のために貯金をしておきたいと考えているお父さんお母さんも多いのではないでしょうか?
そのための方法の一つが、赤ちゃん名義の銀行口座を作ってそこにお金を貯める、いわゆる「赤ちゃん口座」です。
今回は、赤ちゃんの銀行口座についてご紹介します。
その前にひとつだけご紹介です。
この記事を読んでいる方の中には「学資保険選びが分からない」「どこに相談すれば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、タイプ別にどの相談サービスを選んだら良いのかをまとめました。
ご近所の店舗で気軽に相談を受けたい方におすすめ
イオンのほけん相談

大手スーパーのイオンが展開する保険相談サービス「イオンのほけん相談」。
利用者からは「いつも買い物している場所で相談できて便利」「イオンの看板があるので安心」「買い物ついでに気軽に相談できる」など好評です。
オンラインで気軽に相談を受けたい方、安心の国内最大級の上場保険代理店
保険市場

8万件のオンライン相談件数を誇る「保険市場」は、場所を選ばずどこからでも相談できます。
利用者からは「自分にぴったりの保険を選んでもらえた」「子供が小さいのでオンラインの相談はとても助かった」「提案がとても丁寧だった」と大満足の声が多く聞かれる保険相談サービスです。
プレゼントも充実!実績十分のファイナンシャルプランナーへ相談したい方へ
ほけんのぜんぶ

お金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナーが、保険をはじめとした暮らしのお金の相談にのってくれる「ほけんのぜんぶ」。
利用した人からは「とても親身になって相談にのってくれた」「FPの方の知識が深くて話が分かりやすかった」「分からない事を一から丁寧に教えてくれた」など好評価です。
お子様に優しいプレゼントも充実!10000人以上のママに選ばれているサービスなら
ほけんガーデン「プレミア」
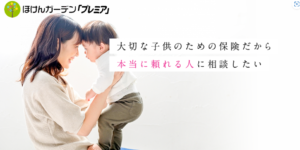
ほけんガーデン「プレミア」はこれまで1万件を超える相談実績がある、ママに人気の保険相談サービス。
利用者からは「自宅まで来てくれたので子供が小さくても安心だった」「聞きにくい質問にも気さくに応じてくれた」「プレゼントが子供向けだったので子供が喜んでいた」と安心の声が多く聞かれています。
この中から自分の好みや状況に合わせて選ぶのがオススメ。
それでも、どうしても迷ってしまって「どのサービスで相談したら良いのか分からない」という方は
この中から選んで、最低2社もしくは3社の話を聞いて比較する方法をおすすめします。
学資保険は1度入ったら基本的にお子様が成人するまで支払い続ける重要なもの。
絶対に失敗するわけにはいきませんよね。
学資保険選びに失敗しないよう今すぐにまずは気軽に問い合わせてみて下さい。
それでは本編にはいりましょう。
赤ちゃん名義の口座を作るメリット

ママになると、周りのお母さんが「赤ちゃんの銀行口座を作った」という話をしているのを耳にする機会があるかもしれません。
そもそも、赤ちゃん名義の口座を作るメリットはどこにあるのでしょうか?
生活費と分けて管理しやすい
メインバンクとは別の口座を給与の振込口座に指定されたり、学生時代に地元の銀行で口座を開いたまま保有していたりと複数の銀行で口座を持つ人は少なくありません。
複数の銀行口座に加えて赤ちゃん用の口座を自分名義で作ってしまうと、どうしても管理が大変になってしまいます。
そこで、赤ちゃんの名前で預金口座を作成することで、他の通帳と区別しやすくなるというメリットがあります。
また、同じ銀行で口座を開く場合でも、通帳のデザインを変えることで区別をつけやすいものです。
子どものための貯金管理がしやすくなる

子どもに最もお金がかかる時期が、大学入学から卒業までの4年間と言われています。
私立大学に行くのか、国立大学に行くのかなどによっても変わってきますが、この4年間に必要なお金は数百万単位です。
そのため、子どもが小さいうちから学資金を貯蓄する人も増えています。
赤ちゃんの口座を作ることで、赤ちゃんの将来の学資金を別に管理しやすくなります。
将来子どもに通帳を渡せる
お金に関する教育はとても大切だと言われていながら、義務教育ではほとんどお金について学ぶ機会はありません。
赤ちゃんの頃に口座を開き、子どもが大きくなったときに渡すことで、自分でお金を管理するように子どもに教えることができます。
赤ちゃんの口座を子どもに渡すことで、お金の大切さややりくりの難しさなどを実体験を通じて知ってもらうことができる点も、赤ちゃん口座の一つのメリットです。
赤ちゃんの口座を開くときに必要なもの

赤ちゃんの口座を開くときには、基本的に以下のものが必要です。
・子どもの本人確認書類
子どものパスポートや保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類が求められます。
・母子手帳など、窓口に行く人が親権者であるとわかる書類
こちらも子どもの本人確認書類と似ていますが、重要なのは子どもと窓口に来た人が親子だと証明できることです。
母子手帳のほか、親権者と子どもが同じ住所に住んでいることがわかる住民票や続柄がわかる書類などが必要になります。
・印鑑
印鑑は両親などが使っているものと同じものでも構いませんが、子どもの預金であることを明らかにしておくためにも、できれば違う印鑑を使って通帳を作る事をお勧めします。
また、ネットバンクなどでは印鑑そのものが不要なこともあります。
このうち、銀行によっては必要ないものもあります。
また、ある銀行では認められても、他の銀行では認められない証明書などもありますので、口座を開設する前に電話などで確認しておくとスムーズです。
赤ちゃんの口座はどんな種類にすればよい?

銀行口座には、普通預金を始め、定期預金などいろいろな種類の口座が用意されています。
このうち、赤ちゃん用の口座はどの種類が適切なのでしょうか。
それぞれの特徴をご紹介します。
普通預金
普通口座は、一般的に利用されている銀行口座です。
自由に預金の預け入れや引き出しができるほか、公共料金を始め、いろいろな料金の引き落とし元口座として設定することもできる便利な口座です。
ただ、貯蓄に適しているかというとその点は弱く、定期預金に比べて金利も低く設定されていることがほとんどです。
赤ちゃんにかかる費用を管理する口座としては使いやすいですが、長期的に貯蓄するための口座としてはあまり適していません。
定期預金

定期預金は、一定の期間引き出すことが制限される口座です。
ほかの口座に比べて比較的金利が高いため、まとまった資金を預け入れておくのに役立ちます。
定期預金の満期には、半年や一年といった短期間を選ぶこともできますし、10年単位の長期間を選ぶことも可能です。
子どもが大きくなるまで眠らせておきたい資金がある場合は、定期預金が適しています。
定期預金の中には、「積立定期預金」という種類もあります。
こちらは、普通預金と連動し、満期になるまで定期的に普通預金から一定額を移動させることによって貯蓄の機能を果たす口座です。
例えば、毎月1万円を普通預金から積立定期預金に移行することで、年間12万円を貯蓄することができます。
毎月一定額を貯蓄に回したい人に向いている預金口座です。
貯蓄預金

貯蓄預金とは、預金額が一定以上になると金利が高くなる口座です。
普通預金と同じように自由に預金や引き出しができますが、定期預金のように引き出し制限はかけることができません。
また、公共料金などの自動引き落としが設定できない預金口座です。
これから徐々に貯金していきたい人にはメリットのある口座といえます。
当座預金
振込みの手続きをしているときなどに見かける当座預金。
当座預金とは、小切手の支払いに使われる口座です。
そのため、赤ちゃんのための口座を開く場合は基本的に関係ありません。
証券口座

一般的な銀行の預金口座とは異なりますが、証券口座を開くのも一つの方法です。
証券口座とは、その名の通り証券会社で開く口座のことです。
証券口座は、積立投信や株式など、投資を行うときに使う口座です。
子どもの学資金を貯めるときには、NISA(少額投資非課税制度)をうまく利用して貯蓄をするという方法がありますが、NISA口座などを開くときに証券会社が使われることが一般的です。
赤ちゃんの口座を開くタイミング

赤ちゃんの将来のために今から準備しておきたい赤ちゃんの口座。
赤ちゃんの口座を開くタイミングとしては、いつが適切なのでしょうか。
お祝い金をもらうタイミング
赤ちゃんが生まれると、親戚をはじめたくさんの人からお祝い金をいただく機会に恵まれます。
家計の状況によっては、このときいただいたお祝い金をそのまま貯蓄に回せると後が楽ですよね。
お祝い金をいただく機会は意外に多く、赤ちゃんが1歳になったときや七五三などでも両親からお祝い金をいただくことがあるかもしれません。
また、毎年正月にはお年玉をいただくことも。
赤ちゃんがまだ小さいうちは、両親が預かっておくものですが、こういったお祝い金などを預けておく口座として赤ちゃんの口座を使うことも一つの方法です。
学費貯蓄を始めた

お祝い金をもらったなどの外部的な要因ではなく、子どものために学資金を貯め始めよう、と決めたときも、赤ちゃんの口座を開設するタイミングです。学資金の貯金方法としては、銀行口座に直接預金する方法もありますが、学資保険を使って貯蓄する方法もあります。
学資保険を利用する場合は、指定した銀行口座から引き落としになるため、赤ちゃん用の口座を利用することにはあまりメリットがないようにも思えます。
しかし、生活費と同じ口座から引き落とす場合はほかの費用の引き落としなどと混同するため、後から管理しにくいというデメリットもあります。
通帳の履歴でもしっかりと学資貯蓄の履歴を残したいという場合は、貯蓄を始めるタイミングで赤ちゃん用の口座を開設するのも一つの方法です。
赤ちゃん用の口座を開設するときの注意点

赤ちゃん用の口座を開設するときに、注意しておきたいポイントがあります。
長期間放置しておくと休眠するおそれがある
「休眠口座」という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。
開設したあとで、取引がないまま一定期間を経過すると、口座が眠っている状態(休眠)と見なされ、預金が入っていようがいまいが関係なく、預金を引き出せなくなってしまうことがあります。
これを休眠口座と呼びます。
口座に入っている預金は、商法という法律に従い、5年間の消滅時効に掛かると考えられています。
この消滅時効が成立すると、預金者の預金に関する権利が消滅することになるのです。
この法律に関わらず、休眠口座をどのように定義するのかは各銀行によって取り決めが異なります。
ただ、一般的に10年間何の取引もなされていない口座を休眠口座とみなす銀行が多くあります。
赤ちゃんの口座を開設し、一定期間は貯金のために使っていたけれど、忙しくなって途中で取引が終わってしまい、気がつけば10年近く経っていた、というケースもあります。
思わぬところでせっかく子どものために貯めていた貯金が不意にならないよう、赤ちゃん用の口座を作るときには「何年取引がなければ休眠口座にみなされてしまうのか」ということは確認しておきましょう。
赤ちゃん用の口座に入れたお金に税金がかかることがある

・贈与税が問題となるケース
子供が小さいうちは、子どもあてのお祝い金などは両親などが管理するのが一般的です。
そこで赤ちゃん用の口座を作って管理することになるのですが、赤ちゃん用の口座に資金を預け入れることで「親から子どもに対して贈与があった」と見なされ、贈与税が課税される可能性があるので注意しましょう。
万が一贈与税が問題となる場合でも、贈与税は年間110万円までなら非課税です。
そのため、赤ちゃん用の口座に資金を入れるのであれば、年間110万円を上限としておけば基本的に贈与税を心配する必要はありません。
ただ、そうなると今度は「名義預金にあたらないか」ということが問題となってきます。
・名義預金が問題となるケース
名義預金は、口座の名義人と実際にその口座を管理している人が異なるときに問題になります。
例えば母親が赤ちゃん用の口座を開設したけれど、その後ずっと母親が通帳を管理して入出金などもすべて行っているとすれば、「預金の名義は子供だが、実際の所有者は母親である」とみなされる可能性があるのです。
名義預金にあたるということは、贈与ではないと見なされるということ。
であれば問題なさそうにも思えます。
しかし、万が一預金を管理している保護者がなくなったときに、赤ちゃんの口座に入っているお金が赤ちゃんのものではなく、保護者のものとなることに。
そのため、相続財産に加えられて相続税の対象となるのです。
名義預金というものがあることを知っておくだけでも違ってきますので、赤ちゃん用の口座を開設するときの注意点として押さえておきましょう。
名義人本人以外解約できないことも

子どもが小さくて自分で預金口座を管理できないうちは、親御さんが代わりに預金口座を管理できたとしても、子どもが成人になった後ではそれまでと同じように親御さんが預金の管理をできない場合があります。
問題となりやすいのが、赤ちゃん名義で作っておいた預金口座を解約するケースです。
銀行によっては、子ども本人以外が解約することができない場合や、子どもの委任状が必要になる場合があります。
後から解約するときにハードルが高いということも押さえておきましょう。
学資保険の受け取り先を子どもの口座にするときは注意する
学資保険に加入しており、受取人を子どもにし、満期学資金の受取先口座を子ども名義の口座にするのは慎重に決めましょう。
契約者と違う人が満期学資金や学資年金などを受け取る場合、贈与となり、贈与税が課税されるからです。
こちらも、年間の受取額が110万円以下であれば課税の心配はありません。
しかし、満期学資金は多くの場合110万円以上を設定していることも多いでしょう。
できれば、満期学資金の受取人は契約者と同じにしておきましょう。
どこがおすすめ?各銀行の特徴やメリット

次に、各銀行で赤ちゃん用の口座を作るときのメリットや特徴などをご紹介します。
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行では、「はじめてのお年玉キャンペーン」というキャンペーンを不定期に開催しています。
新規口座を開設する名義人が0歳の場合、お年玉として1,000円がもらえるというシステムです。
時期によっては対象外になることもありますし、今後内容が変更されることも考えられます。しかし。
開設時期を選べるのであれば、キャンペーンの有無を確認してお得に開設したいところです。
また、ゆうちょ銀行のメリットは、全国に支店があって利用しやすい点です。
都市銀行は大きい反面、地方に行くと支店の数が少なくなります。
地方銀行は地域に根ざして利用しやすいのですが、子どもが成長して大学進学などで地元を離れる可能性があります。
その点ゆうちょ銀行はどこに移動してもさほど不便を感じずに済みます。
三菱東京UFJ銀行

三菱東京UFJ銀行は都市銀行の一つで、都心部に住む人には使い勝手の良い銀行の一つです。
通帳を発行せず、ネットバンキング上で取引や明細を確認することができるため、通帳を失くしたり保管したりという手間がかかりません。
子どもが来店して口座を開設するのが難しい場合は、郵送での手続きも可能です。
ちなみに、子どもが15歳以上になってから口座を開設する場合は、子どもが直筆で口座開設書を記入する必要があります。
三井住友銀行
三井住友銀行も、不定期に赤ちゃん用の口座開設キャンペーンを行っていることがあります。
ゆうちょ銀行のような現金ではありませんが、対象者にはプレゼントが贈呈されることがあるので、キャンペーンをチェックしておきましょう。
三井住友銀行では、同じ支店の他口座に振り込む際は振込手数料が無料です。
親御さんと同じ支店で赤ちゃんの口座を開設しておけば、学資金を貯金する際にネットバンキングで振込をしても費用がかからない点は大きなメリットです。
イオン銀行

イオン銀行の大きなメリットは、大きなショッピングモールには入っているため、窓口が開いている時間が長いこと。
通常の銀行は15時には窓口が閉まってしまいますが、イオン銀行は年中無休で夜も9時まで営業している店舗も少なくありません。
また、提携金融機関のATMでも手数料が一部無料となるなど、普段使いにも使い勝手が良い銀行です。
近くにイオンモールがあるという人は、イオン銀行も選択肢に入れておくといいでしょう。
イオン銀行でも、赤ちゃん用の口座を開設する人に向けて不定期にキャンペーンをおこなっています。
2015年のキャンペーンは定期預金の金利が優遇されるなどの特典がありました。
住宅ローンの金利も非常に安いため、将来家を建てる時のことを考え早い段階から関係を構築しておくのも良いかもしれません。
住宅ローンについては注文住宅ラボが参考になります。
楽天銀行

楽天銀行は、実店舗がないネットバンクのひとつです。
赤ちゃん名義の口座を開設するときにも、ネット上で開設手続きが完了するため、忙しくてなかなか銀行に行けない人には便利な銀行です。
また、開設手続きをするときには印鑑を押したり、申込書を記入したりする必要がありません。
SBI証券
こちらは証券会社の証券口座です。子どもが小さいうちから資産運用をしたいと考えている人には、証券会社で赤ちゃん用の口座を開くという方法があります。
ちなみに、ジュニアNISAを活用したい場合にも、未成年である赤ちゃん名義の口座が必要になります。
SBI証券の場合、赤ちゃんの口座を開設するにあたっては親権者もSBI証券に口座を持っておく必要があります。
また、赤ちゃん用の口座を開設するにあたっては赤ちゃんのマイナンバーがわかる書類が必要となります。手続き自体は難しくありません。
成人と同じく、ネット上で開設手続きが完結します。
まとめ

赤ちゃんの銀行口座を開設するメリットや注意点についてご紹介しました。
赤ちゃんの名前で口座を持つことによって、将来赤ちゃんにかかる学資金の管理がしやすくなったり、貯金がしやすくなるなどのメリットが期待できます。
一方で、名義預金と見なされたり、贈与とみなされたりと注意しておきたい事もありますので、メリットと合わせて注意点もしっかりと把握しておきたいところです。



