マイナス金利政策が実施されてから2年以上の月日が経ちますが、「マイナス金利」の意味を正しく理解できている人は少ないのではないでしょうか。
日常的に耳にする言葉では無いので、私自身も家庭を持って保険や金融を学んでいなければ何のことか分からないまま過ごしていたことでしょう。
「金利がマイナスになる」と言われても、それが自分たちの生活にどのような影響があるのかいまいちピンと来ませんよね。
今記事ではマイナス金利について金融事情に詳しくない方でもわかりやすく、以下の内容を解説します。
| ・マイナス金利政策とは何なのか ・マイナス金利を導入することで私たちにそんな影響を及ぼすのか ・マイナス金利政策はいつまで続くのか |
金融政策というと難しそうでなんとなく遠い存在のように感じますが、金利は身近な生活にもかなりの影響を及ぼします。
お金は生活と直結していて、切り離せないものです。
金融事情に明るくなることでお金の悩みや将来の不安を解消するのに役立つかもしれません。
ぜひ最後まで目を通していただければと思います!
その前にひとつだけご紹介です。
この記事を読んでいる方の中には「学資保険選びが分からない」「どこに相談すれば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、タイプ別にどの相談サービスを選んだら良いのかをまとめました。
ご近所の店舗で気軽に相談を受けたい方におすすめ
イオンのほけん相談

大手スーパーのイオンが展開する保険相談サービス「イオンのほけん相談」。
利用者からは「いつも買い物している場所で相談できて便利」「イオンの看板があるので安心」「買い物ついでに気軽に相談できる」など好評です。
オンラインで気軽に相談を受けたい方、安心の国内最大級の上場保険代理店
保険市場

8万件のオンライン相談件数を誇る「保険市場」は、場所を選ばずどこからでも相談できます。
利用者からは「自分にぴったりの保険を選んでもらえた」「子供が小さいのでオンラインの相談はとても助かった」「提案がとても丁寧だった」と大満足の声が多く聞かれる保険相談サービスです。
プレゼントも充実!実績十分のファイナンシャルプランナーへ相談したい方へ
ほけんのぜんぶ

お金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナーが、保険をはじめとした暮らしのお金の相談にのってくれる「ほけんのぜんぶ」。
利用した人からは「とても親身になって相談にのってくれた」「FPの方の知識が深くて話が分かりやすかった」「分からない事を一から丁寧に教えてくれた」など好評価です。
お子様に優しいプレゼントも充実!10000人以上のママに選ばれているサービスなら
ほけんガーデン「プレミア」
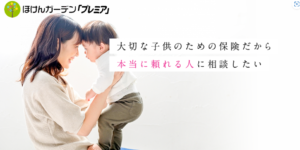
ほけんガーデン「プレミア」はこれまで1万件を超える相談実績がある、ママに人気の保険相談サービス。
利用者からは「自宅まで来てくれたので子供が小さくても安心だった」「聞きにくい質問にも気さくに応じてくれた」「プレゼントが子供向けだったので子供が喜んでいた」と安心の声が多く聞かれています。
この中から自分の好みや状況に合わせて選ぶのがオススメ。
それでも、どうしても迷ってしまって「どのサービスで相談したら良いのか分からない」という方は
この中から選んで、最低2社もしくは3社の話を聞いて比較する方法をおすすめします。
学資保険は1度入ったら基本的にお子様が成人するまで支払い続ける重要なもの。
絶対に失敗するわけにはいきませんよね。
学資保険選びに失敗しないよう今すぐにまずは気軽に問い合わせてみて下さい。
それでは本編にはいりましょう。
マイナス金利とは

「マイナス」とは、0より小さいということを意味することはお分かりかと思います。
では、金利とはそもそも何なのでしょう。
金利とは
「金利」とは、お金の貸し借り・預入などの際に発生する利息を指す言葉です。
これはお金が本来の持ち主の手から離れている際に、離れている間に所持している人が支払うお金の使用料と考えるとわかりやすいでしょう。
私たちが利息を支払う側(借金をしている側)のとき、借りたお金は手元に置いておかず、何かに使っていることと思います。
銀行に預け入れられているお金も同じように、ただ保管されているのではなく銀行が運用しています。
そのため銀行は預金者に対して利息(使用料)を支払う…これが金利です。
100万円の預金を年利0.02%で預け入れしていると仮定すると、利息として年間2万円が受け取れるという計算になります。
「マイナス」金利ということは本来プラスであるはずの金利がマイナスであるということ。
すなわち、お金を預けていると減るということになります。
「急いで銀行預金を全額降ろさなきゃ!」なんて焦ってしまいますよね…。
ご安心ください、私たち一般人が銀行にお金を預けても金利はマイナスになりません=お金は減りません。
マイナス金利は銀行が日本銀行に預けているお金の一部に適用される制度です。
マイナス金利政策は何のために導入されたのか

マイナス金利は景気を回復に向かわせる手段の一つとして2016年1月に発表、同2月に導入されました。
正式には「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」といいます。
日本銀行は日本の中央銀行であり、一般的な銀行とは違った様々な仕事を担っています。
様々な業務のうちのひとつを簡単に言うと、銀行の銀行として動いているのです。
各種銀行などの金融機関が保有する日本銀行当座預金の一部にマイナスの金利を適用する、これがマイナス金利政策です。
日本銀行に預けっぱなしだと金利がマイナスな分お金が減ってしまう…となると、各金融機関はお金を投資や企業へ貸し出したりして金利収入を得たいと考えるはずです。
その結果、お金が世の中に流通するでしょう。
お金が動くようにすることで経済が活性化し、景気が刺激され、デフレ脱却に繋がる。
これがマイナス金利政策のねらいです。
マイナス金利を導入するメリットデメリット

マイナス金利政策が導入されたといういことは、そうすることで日本経済に良い効果をもたらすと判断されたからでしょう。
日本以外には過去にスイス国立銀行、スウェーデン国立銀行、デンマーク国立銀行、ヨーロッパ中央銀行(ECB)の4つの銀行で実施されています。
ですが、良い効果の裏には必ず副作用があるものです。
間接的とはいえ、そのしわ寄せは国民の生活にまわってきます。
マイナス金利政策を導入することで国民が得られるとされるメリットとデメリットにはどんなものが挙げられるのでしょうか。
私たちの生活に影響を与えるであろう点を探りました。
マイナス金利政策のメリット
| ローンの金利が下がる |
マイナス金利政策で最も影響を受けたのは金融機関です。
日銀にお金を預けて得られる金利収入が減ってしまったため、低金利であってもお金は貸し出した方が得策であると考えた金融機関もありました。
これにより低金利でローンが組めるようになり、家を建てる人や設備投資をする企業などが増えたため、不動産業界や建築業界はマイナス金利政策の恩恵を享受したと言えます。
自分の家を建てるだけでなく、個人で賃貸住宅を経営するようになった者も増えました。
マイナス金利政策のデメリット
| 普通預金、定期預金などの金利が下がる 保険の返戻率が下がる |
金利が下がるということは、立場を入れ替えるとメリットがたちまちデメリットになってしまいます。
お金を借りる側としては嬉しい低金利ですが、貸す側(預ける側)の目線で考えると損もあるようです。
普通預金、定期預金などの金利、保険の返戻率が下がる
お金を銀行に預けていると金利が発生しますよね。
この預金に適用される金利、マイナス金利導入前と後では0.02%→0.001%、約20分の1も下がってしまったんです。
銀行預金が100万円あったとすると、1年間預けて受け取れる金利は0.02%で200円、0.001%でたった10円という計算になります。
・・・・・もともとビックリするほど少ないですよね。
日本はここ15年ほどずっとデフレが続いているためこれ以上景気を悪くしないために金利を低くせざるを得なかったのです。
そして、いいかげん経済を活性化させてデフレを脱却させよう!と思い切って導入されたのがマイナス金利政策だったわけですね。
保険の返戻率が下がる
保険商品もマイナス金利の影響をガッツリ受けてしまっています。
積立式の保険で代表的なのが学資保険。
マイナス金利が導入されて少し経った頃、2017年4月くらいから学資保険の返戻率がガクッと下がったり販売停止になる商品もあり、かなりの打撃を受けています。
| そもそも返戻率とは…支払った保険料に対してどのくらいの保険金が受け取れるかの割合です。 100%なら同額、100%を超えている部分は得できる部分であり、返戻率が100%を切ってしまう学資保険は「元本割れ」しているといい、お金が減ってしまうことを意味します。 |
私の子供は2012年生まれなのですが、当時は高いもので返戻率が120%を超えている商品もあり非常に条件良く契約ができました。
しかし、マイナス金利の導入に伴って返戻率の高い保険商品は軒並み販売停止となり、新たに販売されるようになった保険は同じ保険料を支払ってももらえる学資金はビックリするほど少なく…つまり返戻率がガクッと下がってしまいました。
2019年現在、新規で契約できる学資保険は元本割れしてしまっている商品もたくさんあります。
しかし、まだ110%を確保できる学資保険も生き残っています…!
マイナス金利が続く限り返戻率は上がらないでしょうから、お子さんに学資保険を検討している方は返戻率の高い学資保険が販売されているうちに契約を検討してみてくださいね。
マイナス金利政策が私たちに及ぼす影響とは?

金利が低くなることで私たちの生活も間接的に影響を受けることがわかりました。
そこで、低金利になることで具体的に私たちにどんなメリットがあり、どのように活かしていくべきなのかご説明いたします。
庶民目線のマイナス金利メリット解説
住宅ローンの金利が下がり借りやすくなったことで個人の賃貸経営が増えたようですが、個人で賃貸経営なんて遠い世界の話のようだと感じる人も多いでしょう。
私も一般庶民なので現実味が湧かないのが正直なところです。
マイナス金利政策は私たち庶民にとっては具体的にどのようなメリットをもたらしたのでしょうか。
ローンを組むほどの大きな買い物といえば「家を建てる」「車を買う」くらいかと思います。
特に大きいのが住宅ローンです。
住宅ローンは世の中に数あるローンの中でも群を抜いて金利が低いです。
住宅ローンを検討した経験がある方はご存知かと思いますが、住宅ローンの金利には固定金利と変動金利があります。
「固定金利vs変動金利」
変動金利
変動金利を選択すると、返済期間中に定期的に金利が見直されます。
変動金利タイプの住宅ローンは他の住宅ローンよりも低金利に設定されています。
低金利状態がずっと続けば最もお得に借り入れできるのが変動金利タイプです。
固定金利
借り入れ時にあらかじめ決められた固定の金利をずっと維持するタイプです。
低リスクの条件として変動金利タイプよりも少し高めの金利に設定されています。
固定金利には「固定金利期間選択型」と「全期間固定金利型」があります。
意味はそのまま、決められた一定期間のみ固定、返済期間中ずっと固定というかたちです。
| 固定金利 | 変動金利 | |
| メリット | ・返済額が固定されるのでライフプランが立てやすい ・金利が動いてもダメージを受けにくいので安心感がある(低リスク) |
・低金利が続けば返済額は少なく済む ・固定金利よりも低い金利設定 |
| デメリット | ・変動金利よりも高めの金利設定 ・低金利が続いた場合返済額は変動金利よりも多くなる |
・金利が動いた場合、返済額が上がる可能性がある(高リスク) |
依然として低金利が続いているローン事情ですが、いつマイナス金利政策が撤回されて金利が上昇するかはわかりません。
もし今後返済額が増えても対応できそうな余裕がある家庭以外は、一定期間でも固定金利でのローン契約をすることをお勧めします。
とくに子育て世帯であれば、せめて子どもに教育費がかかる期間中は計画的に生活できるよう固定金利を維持できるローンを契約するのが安心です。
また、住宅ローンの金利は家の引き渡し時のものが適用されます。
金利が安い!と耳にして新築しても、新築にはしばらく時間がかかるため実際に建った家の引き渡し時には希望の低金利が維持されているかどうかわからないものなのです。
固定金利を希望しているのならば、マイナス金利が続いているうちにローンを組んでしまいたいとは思いますね。
【おまけ】既に住宅ローンを組んでいる方向けアドバイス
低金利時代に入るより前に住宅ローンを組んだ人には住宅ローンの借り換えを検討してほしいです。
住宅ローンの借り換えには手数料や手間がかかるので、損をしないよう慎重に動く必要があります。
「現在変動金利でローンを組んでいて、将来金利が上昇したら不安」
「マイナス金利以前に組んだ固定金利が高い」
こんな悩みをお持ちの方はぜひ一度シミュレーションしてみましょう。
| ①借り換えでの金利の差が1.0%以上になる ②返済期間が10年以上残っている ③返済金額が1,000万円以上残っている |
上記の3点にに当てはまる方はぜひ借り換えのために動き出してほしいです。
金利が下がる以外の2つのメリット
また、住宅ローンの借り換えを行うと他にもメリットがあります。
・団体信用生命保険の内容を充実させられる
・リフォーム代を上乗せで借り入れできる
団体信用生命保険
団体信用生命保険とは、住宅ローンを契約する際に加入する保険です。
分かりやすく言うと”契約者が死亡した場合は残りのローンがチャラになる!”といった保障を担っています。
住宅ローンの借り換えを行うことで団体信用生命保険の保障内容を見直すことができるのはメリットでしょう。
リフォームローンの上乗せ
リフォームローンは住宅ローンより金利が高く、単独で組むと金利は2%以上になる可能性が高いです。
そこで、住宅ローン借り換えの際にリフォーム代を上乗せした金額でローンを組めば、新たにリフォーム分の資金を借りることができます。
住宅ローン用の低金利でリフォーム費用を手にできるのはかなりお得です。
マイナス金利で住宅ローンが下がっている今、この低金利の恩恵を受ける方法として住宅ローンの借り換えは非常に現実的でしょう。
リフォームに関しては下記サイトが参考になります。
マイナス金利政策はいつからいつまで続く?

2016年から3年以上続いているマイナス金利政策ですが、いったいいつまで続くのでしょう。
もともとデフレ脱却のために導入された政策であり、目標は物価上昇率2%でした。
しかし、結果として物価の伸び率は0%台後半と大変伸び悩んでおり、到底目標に到達するとは思えません。
いつまで続けられるかは不明ですが、目標達成で終えるよりも副作用が大きすぎて辞めざるを得なくなる未来の方が想像できますね…。
まとめ

マイナス金利がどのような政策なのか、目的や我々にもたらす影響をご紹介しました。
一般人である我々にとってはメリットもデメリットもある状態となり、そこまで強い打撃は無いように見えるマイナス金利政策。
しかし直接的な影響を受けている金融機関がいつまでこの超低金利状態に耐えられるか……。
また、金利が低い状況で物価の上昇が実現された場合、銀行に預けっぱなしにしていたお金の価値は下がってしまいます。
消費する・投資することで資産が守られていくのです。
そして国民の消費活動や投資がお金を流し、経済が回復していくのが理想的な未来ですね。
なにもしないでいて損してしまうことが無いよう、金利の低い今のうちに対策を立てていきましょう。
私もいち日本国民として、小さい子供を持つ親として、日本の将来の経済状況は心配です。
自分たちにできることを少しずつはじめていきたいですね。
ひとりひとりのその気持ちが、きっと経済を動かします!
ここまでお読みくださりありがとうございました。



